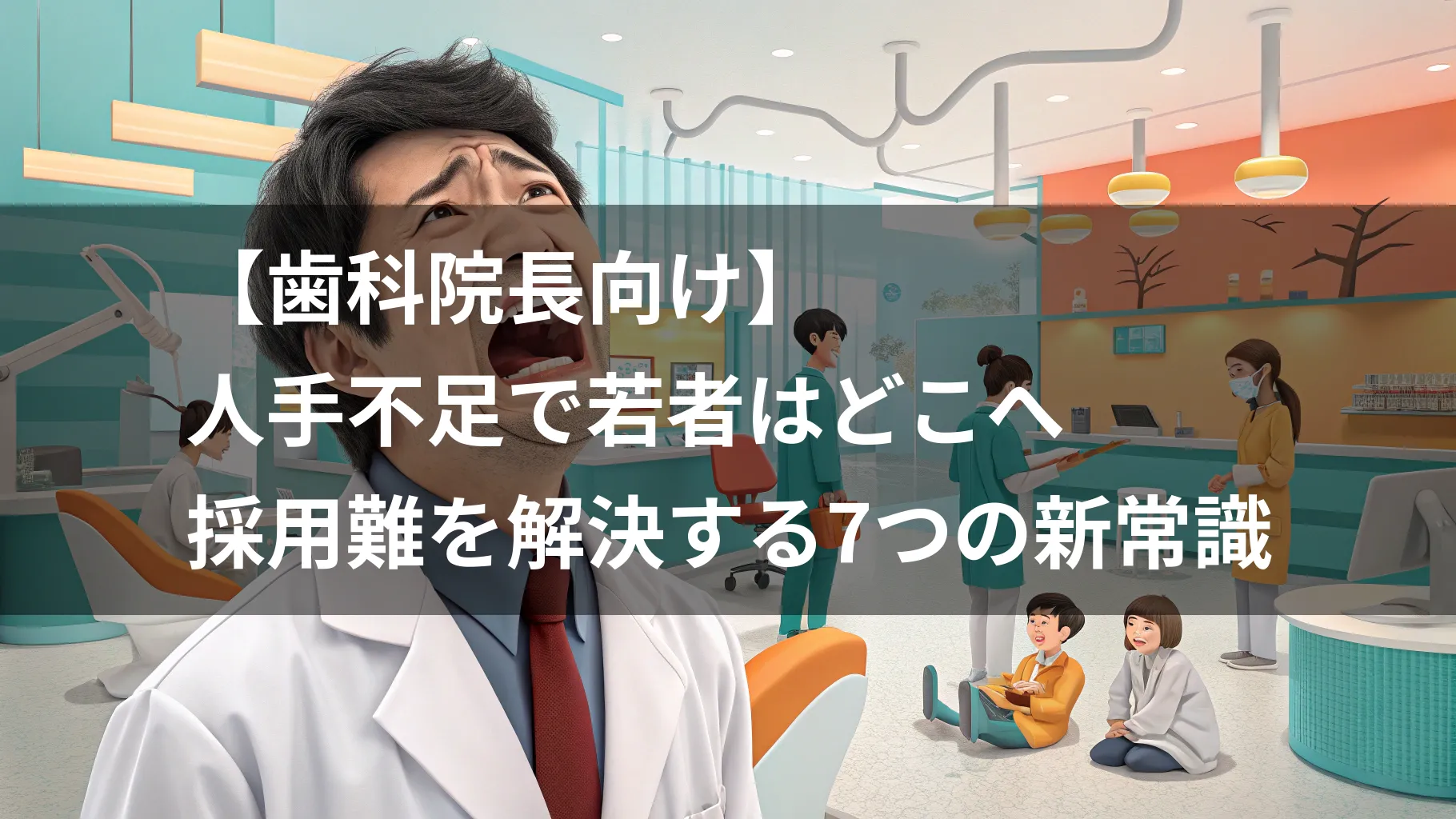歯科衛生士や若手スタッフの採用がうまくいかず、「若者は一体どこへ消えたんだ」と頭を悩ませていませんか。
この記事では、人手不足の本当の理由である若者の価値観の変化を解き明かし、歯科衛生士から「ここで働きたい」と選ばれる医院になるための7つの新常識を具体的にお伝えします。
 あいこ
あいこ給料を上げれば来てくれると思ってましたが、違うのでしょうか?



もちろん待遇も大切ですが、それ以上に「ここで成長できるか」を若者は見ています
- 人手不足の本当の理由と若者のリアルな価値観
- 歯科衛生士の採用と定着を成功させる7つの新常識
- 明日から始められる魅力的な職場環境の作り方
歯科衛生士の採用難は解決可能|若者に選ばれる医院への変革


「若者がいない」のではなく、「若者が選ぶ魅力的な職場が他にある」というのが、採用がうまくいかない本当の理由です。
先生の医院でも、若者の価値観の変化を深く理解し、彼らが「ここで働きたい」と心から思えるような職場環境を整えれば、採用難は解決できます。
人手不足は、医院が進化する絶好の機会なのです。
人手不足を問題と捉えず、医院が進化する機会と考える
多くの院長が直面する人手不足は、単なる問題として片付けるべきではありません。
むしろ、医院の組織としてのあり方を見直すべきサインと捉えることが重要になります。
スタッフが定着しない現状は、院内に改善すべき点が明確にある証拠です。
実際にZ世代と呼ばれる若者のうち、新規大卒者の32.3%が3年以内に離職しています。
この事実を重く受け止め、課題解決に取り組むことが、医院の成長につながります。



でも、具体的に何から手をつければいいのか分からないです…



まずは現状を問題ではなく、成長のチャンスと捉えることから始めましょう
課題を一つひとつ乗り越えていくプロセスそのものが、スタッフの満足度を高め、最終的には患者さんへの医療サービスの質を向上させるのです。
採用における視点転換|「若者がいない」から「若者に選ばれる」への視点転換
「求人を出しても若者からの応募がない」と嘆く前に、視点を180度転換してみる必要があります。
現代において、採用活動は、医院が求職者から選ばれる立場にあるという事実を認識しなくてはなりません。
給与や休日といった条件面だけでは、若者の心をつかむことは難しい時代です。
現代の若者が仕事に求めるもので最も多いのは「自己成長できること」で、その割合は56.6%にも上ります。
彼らは、自分のキャリアがどう形成されていくのかを真剣に考えています。
自院で働くことでどのようなスキルが身につき、どう成長できるのかという未来像を明確に提示することが、採用成功への第一歩となります。
院長の意識改革から始まる組織作り
魅力的な職場環境への変革は、他の誰でもなく、院長である先生自身の意識改革から始まります。
スタッフが辞めていくのを彼らのせいにせず、まずは自分に何ができるかを考える姿勢が不可欠です。
魅力的な組織作りは、トップである院長のリーダーシップから始まるからです。
難しいことを考える必要はありません。
まずは、スタッフ一人ひとりの声に真摯に耳を傾けることから始めてみましょう。
例えば、月に1回、5分だけでもスタッフと1対1で話す時間を作ると、医院の課題が見えてきます。



スタッフとの対話は、少し苦手意識があります…



完璧な院長である必要はありません。まずは真摯に耳を傾ける姿勢が大切です
院長の姿勢が変われば、スタッフのエンゲージメントも高まり、医院全体の雰囲気が明るくなります。
その変化は必ず若き求職者にも伝わり、自然と人が集まるクリニックへと変わっていくでしょう。
若者はどこへ消えたのか|人手不足の背景にある価値観の変化


人手不足の根本的な原因は、若者の絶対数が減っていることだけではありません。
より本質的な問題は、仕事に求める価値観そのものが根底から変化したことにあります。
給与や安定よりも、自身の成長や働きがいを重視する若者の新しい常識を理解することが不可欠です。
| 価値観の項目 | 従来の価値観(40〜50代) | Z世代の価値観 |
|---|---|---|
| 仕事の目的 | 安定した生活と収入の確保 | 自己実現とスキルアップ |
| 会社との関係 | 終身雇用、会社への帰属意識 | プロジェクト単位の貢献、転職でキャリアアップ |
| 評価の基準 | 勤続年数や労働時間 | 成果や貢献度、個人のスキル |
| キャリア形成 | 一つの会社で昇進 | ジョブホッピング、副業、フリーランス |
| 重視する要素 | 給与、福利厚生、企業の安定性 | ワークライフバランス、成長機会、社会貢献 |
若者が「いない」のではなく、彼らの価値観に合う魅力的な職場が歯科業界以外に増えているのが実情です。
この変化を正しく捉えることが、採用問題を解決する最初のステップとなります。
少子高齢化と都市部・大企業への人材集中
まず向き合うべきなのは、少子高齢化による生産年齢人口そのものの減少です。
これは、採用活動における構造的な課題といえます。
1990年代初頭には1,800万人以上いた15歳から24歳の人口は、2023年には約1,132万人まで減りました。
その限られた若者も、キャリアや生活の利便性を求めて都市部へ流出しています。
特に東京23区では、転入者のうち約半数が20代で占められる状況です。
さらに、若者の多くは安定性とブランドイメージを求めて大企業を目指します。
従業員5,000人以上の大企業の求人倍率が約0.4倍であるのに対し、300人未満の中小企業では約6.2倍にものぼり、採用の難易度に大きな差が開いています。
こうしたマクロな環境要因を理解したうえで、中小企業である歯科医院がどう戦うべきか、戦略を立て直す必要があります。
給与よりも「自己成長」を求めるZ世代の仕事観
Z世代とは、一般的に1990年代半ばから2010年代序盤に生まれたデジタルネイティブの若者たちを指し、彼らの仕事観は上の世代と大きく異なります。
給与水準はもちろん重要ですが、それが仕事を選ぶ絶対的な決め手ではなくなっています。
実際に、現代の若者が働く上で求めるものとして「自己成長できる」と答えた割合は56.6%で最多となり、これは40代や50代よりも12ポイント以上高い数値です。
彼らにとって仕事とは、単にお金を稼ぐ手段ではなく、自身の市場価値を高め、将来のキャリアを豊かにするための投資という意味合いを持っています。



給料を上げれば若者は集まると思っていましたが、それだけではないのですね…



はい、Z世代は将来への投資として「成長できる機会」を給与と同等、あるいはそれ以上に重視しているのです
医院がスタッフの成長をいかに後押しできるか、その姿勢が問われています。
早期離職の本当の理由|人間関係と正当な評価
Z世代を含む新規大卒者のうち、3年以内に32.3%が離職するというデータがあります。
表向きの退職理由は「労働時間や賃金の条件が合わなかった」などが挙げられますが、本当の理由は他にあることが少なくありません。
ある調査では、退職者が本音で語る離職理由のトップは「人間関係が悪い」で、その割合は46%に達しました。
多くの若者は、不満を正直に伝えられないまま職場を去っているのです。
特に、院長や先輩スタッフとのコミュニケーション不足、意見を言えない圧迫感、そして自分の頑張りが正当に評価されないことへの不満が、静かに彼らのモチベーションを蝕んでいきます。



辞めていくスタッフは、いつも「家庭の事情」や「体調不良」と言っていましたが…



本音を言えない雰囲気そのものが、実は離職の引き金になっていることもあります
給与や待遇といった条件面だけでなく、スタッフが安心して本音を話せる心理的安全性と、成果が報われる透明な評価制度の構築が、定着率向上の鍵を握ります。
ジョブホッピングやフリーランスという新しいキャリア形成
ジョブホッピングとは、2〜3年といった短い期間で転職を繰り返し、キャリアアップや年収増を目指す働き方です。
Z世代にとって転職はもはやネガティブなものではありません。
実際にZ世代の転職活動者数はこの5年間で約2倍に増えており、転職を「自分のキャリアの方向性を主体的にコントロールする手段」と捉えています。
また、特定の組織に属さず、専門性を武器に働くフリーランスという選択も一般的になりました。
歯科衛生士のような専門職も例外ではなく、特定の医院に縛られずに、複数の医院で働いたり、自らのスキルを活かして独立したりするキャリアパスも現実的な選択肢となっています。
終身雇用を前提としていた時代は終わり、現代の若者は常に「この職場よりもっと良い環境はないか」という視点を持っていることを、経営者は認識する必要があります。
スキルアップを求めてIT業界やスタートアップへ
成長意欲の高い若者たちが、今こぞって目指しているのがIT業界やスタートアップ企業です。
これらの業界には、若者を惹きつける明確な理由があります。
IT業界は慢性的な人手不足から若手でも活躍の場が多く、スタートアップ企業は年齢に関係なく裁量権の大きな仕事を任される文化があります。
例えば、株式会社タイミーの社内平均年齢は30.1歳です。
若いうちから責任ある立場で経験を積み、スピーディーに成長できる環境が、彼らにとっては何よりの魅力なのです。
自分のスキルが直接事業の成長に繋がり、それが正当に評価される、そうした環境に人材が集中するのは自然な流れといえます。
歯科業界も、これら成長産業の仕組みから学び、若手がやりがいと成長を実感できる環境を整えていくことが求められます。
日本の将来性への不安と海外移住への関心の高まり
若者の視線は、国内の他業界だけでなく、海外にも向けられています。
日本の将来性への漠然とした不安から、海外での就職や移住を真剣に考える若者が増加しているのです。
2023年時点で海外に永住する日本人は約57万人を超え、20年連続で増加傾向にあります。
特に20代から30代の若者層を対象とした調査では、86.7%が「海外移住や永住の可能性がある」と回答しました。
その背景には、日本の経済的な停滞や硬直化した労働環境への不満、そしてより良いワークライフバランスや実力が正当に評価される成果主義の環境を求める気持ちがあります。
このグローバルな人材獲得競争の時代において、国内の歯科医院だけを競合と見るのではなく、世界基準の魅力的な職場を作っていくという高い視座が、これからの医院経営には必要です。
歯科衛生士の採用と定着を成功させる7つの新常識


歯科衛生士の採用と定着を成功させるためには、従来の常識にとらわれず、現代の若者の価値観に寄り添った新しいアプローチが不可欠です。
給与や待遇といった条件面だけでなく、スタッフ一人ひとりの「エンゲージメント(働きがい)」を高めることが、長期的な活躍に繋がる最も重要な鍵となります。
ここでは、若者に選ばれる医院になるための7つの新常識を紹介します。
| 新常識 | ポイント |
|---|---|
| 新常識1 | 給与以外のエンゲージメント要素の重視 |
| 新常識2 | 院長の想いやビジョンを伝える情報発信 |
| 新常識3 | 成長を実感できるスキルアップ支援 |
| 新常識4 | 頑張りが報われる透明性の高い評価制度 |
| 新常識5 | 心理的安全性が確保された職場風土 |
| 新常識6 | 採用段階での価値観のマッチング |
| 新常識7 | ワークライフバランスを尊重した働き方 |
これらの新常識を一つひとつ実践していくことで、先生の医院は若手歯科衛生士にとって魅力的な職場へと変わっていきます。
人手不足を医院が進化する好機と捉え、組織改革を進めていきましょう。
新常識1|給与や待遇以外のエンゲージメント向上策
エンゲージメントとは、スタッフが医院の目標達成に向けて「自発的に貢献したい」と感じる意欲や熱意のことです。
給与や待遇はもちろん重要ですが、それだけで若者の心をつなぎとめることは難しくなっています。
Z世代の退職理由の本音として最も多いのは「人間関係の悪さ」で、その割合は46%にものぼります。
このデータが示すように、金銭的な報酬以上に、院長からの感謝の言葉、成長の機会、良好な人間関係といった「精神的な報酬」が、彼らのエンゲージメントを大きく左右するのです。



給料さえ良ければ良い、という時代ではないのですね…



はい、若者は金銭的報酬と同じくらい「承認」や「成長」といった精神的な報酬を求めています
日々の業務の中で「ありがとう」「助かるよ」といった感謝の言葉を伝える、スタッフの意見に真摯に耳を傾けるといった小さな積み重ねが、スタッフのエンゲージメントを高め、定着に繋がる第一歩です。
新常識2|院長の想いやビジョンを伝える情報発信戦略
採用活動は、単に空いたポストを埋める作業ではありません。
医院の未来を共に創る仲間を探す「採用ブランディング」の一環と捉える必要があります。
そのためには、院長自身の想いや医院が目指すビジョンを、求職者に明確に伝える情報発信が欠かせません。
ホームページやSNSで発信するべきなのは、給与や休日といった条件だけではありません。
なぜこの場所で開業したのか、どんな患者様を笑顔にしたいのか、スタッフにどう成長してほしいのか。
院長自身の言葉で語るストーリーは、求職者の心に深く響き、強い共感を生み出します。



SNSで何を伝えたら良いのか、いつも悩んでしまいます…



まずは先生がどんな想いで開業したのか、そのストーリーを発信することから始めてみませんか
院長の熱い想いやビジョンに共感して集まった人材は、仕事に対する目的意識が高く、困難な状況でも簡単には辞めません。
一貫性のある情報発信を続けることが、医院の理念に合った人材を引き寄せる強力な磁石となります。
新常識3|成長を実感できるスキルアップ支援制度の構築
現代の若者が仕事に求めるものの上位に常に挙がるのが「自己成長」です。
この医院で働き続ければ、歯科衛生士として成長できるという未来像を提示できるかどうかが、若者に選ばれるための重要な分かれ道になります。
実際にZ世代の約6割が、自身のスキルアップのために何らかの学習に取り組んでいるという調査結果もあります。
外部セミナーへの参加費補助、認定衛生士などの資格取得支援、定期的な院内勉強会の開催など、医院として成長を後押しする具体的な制度を構築しましょう。
| 支援制度の例 | 内容 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 研修・セミナー参加費補助 | 外部研修やセミナーの費用を医院が全額または一部負担 | 最新知識の習得、モチベーション向上 |
| 資格取得支援制度 | 認定資格の取得費用や学習時間を支援 | スタッフの専門性向上、医院の信頼性アップ |
| 院内勉強会・OJT | 定期的な症例検討会や先輩からの実技指導 | スキルの平準化、チームワーク強化 |
| メンター制度 | 先輩スタッフが新人を1対1でサポート | 早期離職防止、心理的な不安の解消 |
スタッフの成長への投資は、短期的にはコストに見えるかもしれません。
しかし、スキルアップしたスタッフが提供する医療の質は向上し、患者満足度を高め、結果として医院全体の成長に繋がる最も確実な投資となるのです。
新常識4|頑張りが報われる透明性の高い評価制度の導入
若者が職場に抱く不満の一つに「頑張りが正当に評価されない」というものがあります。
院長が個人の感覚だけで評価を下していては、スタッフは「何を頑張れば評価されるのか分からない」と混乱し、モチベーションを失ってしまいます。
ここで重要なのは、評価制度の「公平性」と「透明性」です。
どのようなスキルを習得し、医院にどう貢献すれば評価が上がり、給与や賞与に反映されるのか。
その基準を明文化し、全スタッフに公開することで、誰もが納得感を持って目標に向かって努力できるようになります。



スタッフの頑張りをどう評価すれば良いのか、基準が曖昧で…



評価項目をスタッフと一緒に作ることで、納得感の高い制度になりますよ
評価シートを作成し、技術スキル、患者コミュニケーション、後輩指導、業務改善提案といった項目を設けるのが効果的です。
半期に一度、そのシートを元に面談を行うことで、スタッフは自身の成長と課題を客観的に把握でき、次のステップへと進む意欲が湧いてきます。
新常識5|心理的安全性を確保する風通しの良い職場風土
心理的安全性とは、組織の中で自分の考えや気持ちを「安心して表明できる状態」のことを指します。
ミスを過度に恐れたり、反対意見を言うことをためらったりするような職場では、スタッフは萎縮してしまい、本来の能力を発揮できません。
若者の離職理由の本音第1位が「人間関係」であることからも、心理的安全性の確保は最重要課題です。
院長が率先して「失敗は成長の糧」「どんな小さな疑問でも歓迎する」という姿勢を示すことが大切になります。
朝礼でポジティブな話題を共有する、ミスが起きた際に個人を責めずにチームで再発防止策を考える、といった取り組みが有効です。



スタッフが何を考えているのか、本音が聞けていない気がします



院長からご自身の弱みや失敗談を話すなど自己開示することで、スタッフも本音を話しやすくなります
スタッフ全員が「この場所は安全だ」と感じられる職場風土を築くことで、情報共有が活発になり、業務効率や医療の質の向上にも繋がります。
結果として、スタッフの定着率も大きく改善されるのです。
新常識6|採用段階でのミスマッチを防ぐ価値観の見極め
採用してもすぐに辞めてしまうケースが多い場合、採用段階でのミスマッチが原因である可能性が高いです。
スキルや経験だけで採用を決めると、医院の文化や価値観に合わず、お互いにとって不幸な結果を招いてしまいます。
採用活動は、スキルチェックだけでなく、医院の理念と応募者の価値観がマッチしているかを見極める場と捉え直しましょう。
面接では「これまでの仕事で最もやりがいを感じた瞬間は?」「どんなチームで働きたいですか?」といった質問を通して、応募者の人柄や仕事観を深く理解することが重要です。



面接で良い人だと思っても、すぐに辞めてしまうことがあります…



スキルの確認だけでなく、医院の文化に合うかという視点を持つことが大切です
同時に、医院側も「私たちは患者様を第一に考えます」「チームワークを何よりも大切にしています」といった価値観を正直に伝える必要があります。
お互いの価値観をすり合わせ、共に成長できると確信できた人材こそ、医院にとっての財産となるのです。
新常識7|ワークライフバランスを尊重した柔軟な働き方の提供
「仕事のためにプライベートを犠牲にする」という考え方は、もはや過去のものです。
現代の若者は、仕事と同じくらいプライベートの時間を大切にし、その両立(ワークライフバランス)を強く求めています。
離職理由の上位に「労働時間・休日・休暇の条件」が挙がるように、働き方の柔軟性は求職者にとって大きな魅力です。
例えば、週休3日制の導入、育児や介護と両立できる時短正社員制度の創設、残業をゼロにするための業務効率化など、スタッフのライフステージに合わせた多様な働き方を提供できないか検討してみましょう。



人手が足りないのに、休みを増やすのは難しいのでは…



働き方を柔軟にすることで、これまで働けなかった優秀な人材を採用できるチャンスにもなります
柔軟な働き方を認めることは、単なる福利厚生ではありません。
優秀な人材の確保と定着に直結する経営戦略です。
スタッフが心身ともに健康で、充実した毎日を送れる環境を整えることが、医院全体の活気と生産性向上に繋がります。
明日から始める魅力的な職場環境の作り方


若者の価値観に合わせた職場環境への変革は、一足飛びには実現できません。
しかし、明日からでも始められる小さな一歩があります。
大切なのは、スタッフ一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、行動に移す姿勢を示すことです。
まずは、これまで見てきた若者の価値観や離職理由を踏まえ、具体的な改善策を実行していきましょう。
スタッフが「この医院で働き続けたい」と心から思える環境を整えることが、採用難を解決する最も確実な道筋です。
まずはスタッフとの1on1ミーティングの導入
1on1ミーティングとは、院長とスタッフが1対1で定期的に行う対話の時間です。
業務の進捗確認だけでなく、キャリアの悩みやプライベートなことまで、安心して話せる場を作る目的があります。
まずは月に1回、30分程度の時間から始めてみましょう。
スタッフの離職理由として最も多い「人間関係の悩み」を解消し、心理的安全性を確保する上で、この対話の時間は欠かせません。



スタッフの本音を聞くのが少し怖い…どう話せばいでしょうか?



最初は仕事で困っていることから聞き、少しずつ信頼関係を築いていきましょう
院長がスタッフの成長と将来を真剣に考えている姿勢が伝われば、スタッフのエンゲージメントは高まり、離職率の低下につながります。
セミナー参加費用の補助制度の明確化
成長意欲の高い若手にとって、スキルアップできる環境が用意されているかは、職場を選ぶ上で極めて重要な判断基準です。
ある調査では、現代の若者(Z世代)の約6割がスキルアップのために何らかの行動を起こしているという結果が出ています。
「セミナー参加費用を医院が全額補助する」「資格取得にかかる費用を年間10万円まで補助する」といった具体的な制度を設けて、成長意欲を積極的に応援しましょう。



費用負担が大きくて、なかなか許可できないのが本音です…



まずは年間5万円までなど上限額を決めて、医院の状況に合わせて無理なく始められます
この制度は、スタッフのスキル向上によって医院全体の医療の質を高めるだけでなく、採用活動において「スタッフの成長を投資と考える医院」として強力なアピールポイントになります。
採用サイトやSNSでの情報発信内容の見直し
採用活動とは、医院が応募者を選ぶだけでなく、応募者から選ばれる場でもあります。
そのためには、給与や休日といった条件だけでなく、医院の理念や働くことで得られる成長を発信することが不可欠です。
求職者は、給与額そのものよりも「自分の頑張りがどう評価され、給与に反映されるのか」を知りたいと考えています。
InstagramやTikTokなどのSNSを活用し、院内研修の様子やスタッフが生き生きと働く姿を動画で発信するのも有効な手段です。
| 発信内容 | Before(条件のみ) | After(魅力・成長を伝える) |
|---|---|---|
| 給与 | 月給25万円~ | 経験や資格取得を反映した明確な評価制度と昇給実績 |
| 休日 | 完全週休2日制(水・日・祝) | 有給取得率100%、昨年度はスタッフ全員が9連休取得 |
| 教育制度 | 研修制度あり | 外部セミナー費用全額補助、月1回の院内勉強会の様子 |
| 医院の雰囲気 | スタッフ仲良し | 院長との1on1や定期的なランチ会でのコミュニケーション |
情報発信を見直すことで、医院の価値観に本当に共感してくれる人材からの応募が増え、採用後のミスマッチを未然に防ぎます。
自院の魅力と課題を客観的に洗い出す方法
魅力的な職場環境を作るには、まず思い込みを捨てて、自院の現状を客観的に把握する必要があります。
そのための有効な手段が、経営分析で用いられるSWOT分析です。
SWOT分析は、「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの視点から自院を分析する手法です。
院長一人で考えるのではなく、スタッフ全員で意見を出し合うと、より多角的な視点が得られます。
| SWOT分析の項目 | 具体例 |
|---|---|
| 強み (Strength) | 最新の滅菌設備、院長が日本歯周病学会認定医 |
| 弱み (Weakness) | スタッフの育成マニュアルがない、SNSでの情報発信ができていない |
| 機会 (Opportunity) | 近隣に大規模マンションが建設予定、訪問診療へのニーズ増加 |
| 脅威 (Threat) | 徒歩圏内にホワイトニング専門の歯科医院が開業、歯科衛生士の全国的な不足 |
この分析によって明らかになった「強み」は採用サイトでアピールし、「弱み」は改善の目標とすることで、医院は着実に成長していきます。
よくある質問(FAQ)
- 歯科衛生士の頑張りを正当に評価したいのですが、具体的にどのような評価制度を作れば良いのでしょうか?
-
スタッフの納得感を高めるには、評価の基準を明確にすることが大切です。
技術面(SRPの技術、TBIの指導力など)と、貢献度(後輩指導、業務改善提案、患者さんからの評判など)の両面から評価項目を設定することをおすすめします。
大切なのは、院長だけで決めずにスタッフと一緒に評価項目を考えるプロセスです。
これにより労働環境の改善に繋がり、給与への納得感も高まります。
- 1on1ミーティングを導入しても、スタッフが本音を話してくれない場合はどうすれば良いですか?
-
多くの院長が同じ悩みを抱えていますので、ご安心ください。
まずは院長先生ご自身の失敗談や弱みを話すなど、自己開示を試みてみましょう。
スタッフが何か話してくれた際は、決して否定せずに最後まで聴く「傾聴」の姿勢が重要です。
すぐに解決策を提示するのではなく、気持ちに寄り添うことで、徐々に信頼関係が築かれ、若者の離職理由で最も多い人間関係の悩みを解消するきっかけになります。
- 大手法人のような好条件を提示できない中小事業者は、採用でどう戦えば良いのですか?
-
給与や休日などの条件面だけで勝負する必要はありません。
中小事業者の採用難を乗り越えるには、大手にはない魅力を打ち出すことが重要です。
例えば「院長との距離が近く、直接経営を学べる」「一人ひとりの成長に合わせたキャリアプランを一緒に考えられる」「意思決定が早く、新しい挑戦をしやすい」といった点をアピールします。
院長の想いを込めた採用戦略の見直しを行い、医院独自のストーリーを伝えましょう。
- ワークライフバランスを重視したいですが、人手不足で休みを増やせません。
-
いきなり休日を増やすのが難しくても、できることはあります。
まずは予約システムやキャッシュレス決済などを導入し、業務を効率化して残業時間を削減することから始めましょう。
スタッフの負担が減ることが、働きやすさに直結します。
人手不足の原因が若者にあるのではなく、働き方の柔軟性が求められているのです。
こうした取り組みは、若者の定着率向上にも繋がります。
- 若手スタッフの「スキルアップしたい」という要望に応えたいのですが、どんな研修を用意すれば良いですか?
-
若者の働き方や価値観は多様化しており、全員に同じ研修を受けさせるよりも、個々の目標に合わせた支援が効果的です。
1on1ミーティングなどで、本人が将来どんな歯科衛生士になりたいのかを聞き出しましょう。
歯周病治療、インプラント、ホワイトニングなど、個々の興味に合わせた外部セミナーへの参加を医院として支援するのです。
こうしたスキルアップ機会の提供が、成長意欲の高い人材にとって大きな魅力となります。
- 新しい取り組みに、ベテランスタッフから反対されたときはどう対応すべきですか?
-
まずは、なぜ新しい取り組みが必要なのか、その背景にある「若手人材の不足」という医院共通の課題を丁寧に説明することが大切です。
そして、ベテランスタッフが培ってきた経験や知識への敬意を伝え、「これまでのやり方の良い部分と、新しい方法を組み合わせて、もっと良い医院にしていきたい」という形で協力を仰ぎましょう。
変革の目的が、スタッフ全員の働きやすさに繋がることを伝えることが重要です。
まとめ
この記事では、若手歯科衛生士の採用が難しい本当の理由と、その解決策を解説しました。
大切なのは給与や待遇といった条件面だけでなく、スタッフ一人ひとりの「自己成長」や「働きがい」をいかに引き出すかです。
- 給与以上に「自己成長」を求める若者のリアルな価値観
- 医院のビジョンを発信し、求職者から「選ばれる」ための採用戦略
- 頑張りが報われる透明な評価制度とスキルアップ支援の構築
魅力的な職場への変革は、まずスタッフの声に真摯に耳を傾けることから始まります。
この記事を参考に、若手スタッフが長く働きたいと思える医院作りへの第一歩を踏み出しましょう。